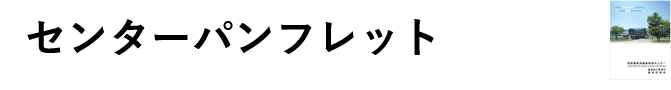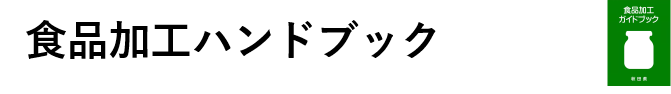研究センター紹介 -沿革
| 大正12年 | 通常秋田県議会醸造試験場設置建議案可決 |
|---|---|
| 昭和2年10月 | 秋田県工業試験場醸造部として、秋田市上中城町に創設 |
| 昭和6年5月 | 秋田県醸造試験場として独立。研究員5名清酒、味噌、調味料、清涼飲料水に関する研究開始 |
| 昭和25年11月 | 秋田市本町に新築移転 |
| 昭和29年11月 | 秋田市長野町に新築移転 |
| 昭和40年4月 | 秋田市八橋(旧醸造試験場)に新築移転研究員7名酒類部門、発酵食品部門 |
| 昭和41年4月 | 系科制施行(管理系、醸造科、分析科) |
| 昭和43年4月 | 改組(管理系、指導科、研究科) |
| 昭和45年4月 | 改組(管理系、酒類科、発酵食品科) |
| 昭和49年 | 食品加工部門を設置(管理科、酒類科、発酵食品科、食品加工科)研究員10名 |
| 昭和60年 | 県、バイオテクノロジー研究構想と試験研究体制の強化について検討 |
| 昭和61年 | 秋田県議会(高度技術産業・交通対策特別委員会)がバイオテクノロジー研究の推進と県食品産業振興策について提言 醸造試験場研究体制の強化拡充決定(微生物応用) 醸造試験場の整備強化構想について検討開始 |
| 平成元年5月 | 県食品加工産業懇談会発足(構成産学官) |
| 平成元年12月 | 県食品関係団体と県議会商工観光議員連盟、醸造試験場の整備強化策提案 |
| 平成2年4月 | 県醸造試験場整備検討委員会発足、検討開始 県食品研究所構想策定(商工労働部) |
| 平成2年8月 | 県食品研究所整備検討委員会発足、検討開始 |
| 平成3年4月 | 県総合食品研究所整備基本構想策定 農政部へ移管 |
| 平成4年2月 | 県議会、県総合食品研究所設置事業調査予算可決 |
| 平成5年2月 | 県議会、県総合食品研究所設置事業予算可決 |
| 平成5年4月 | 県食品研究所建設事業着手 |
| 平成7年4月 | 県総合食品研究所開所 (内部組織:食品加工研究所・醸造試験場・総務管理課) |
| 平成8年4月 | 行政改革により、農業技術交流館(現農業研修センター)・加工部門を分室として統合 |
| 平成13年4月 | 生物機能第二担当新設 |
| 平成18年4月 | 農林水産関係機関を統合し、秋田県農林水産技術センター 総合食品研究所に改組、改称 |
| 平成21年4月 | 秋田県総合食品研究所に改組、改称 |
| 平成22年4月 | 産業労働部の研究機関となり、秋田県総合食品研究センターに改組、改称 |
| 平成24年4月 | 観光文化スポーツ部の研究機関となる |
R6年度研究課題
| 区 分 | 研究課題名 | 期 間 |
|---|---|---|
| 政策 | 生産地加工による県産農林水産物の高付加価値化 | R04-06 |
| 政策 | 花卉の食品利用技術開発 | R05-07 |
| 政策 | 新規麹菌を用いた新たな秋田オリジナル甘酒の開発 | R04-06 |
| 政策 | 輸出向け発酵調味料の開発 | R05-06 |
| 政策 | 新しい生活様式に対応した低アルコール及び複合型アルコール飲料の開発 | R04-06 |
| 政策 | 秋田県産清酒の販路拡大に向けた海外市場向け清酒に関する調査 | R06-07 |
| 政策 | ライフステージに応じた機能性食品の開発 | R04-06 |
| 政策 | 網羅的解析データを活用した県産食品・素材の競争力強化手法の開発 | R06-08 |
| 政策 | 発酵特性デザインを可能とする味噌用酵母育種技術の検討 | R06 |
交通案内
○所在地
〒010-1623
秋田市新屋町字砂奴寄4-26
TEL 018-888-2000 FAX 018-888-2008
○秋田駅から約7km バスは秋田中央交通をご利用ください。
秋田駅西口のりばから「県立プール線」 終点「県立プール前」下車徒歩2分
所要時間約30分
時刻表はこちらから(秋田中央交通様HPへのリンク)
*所内に自販機等ございません。
また、近所にコンビニ等もございませんのでご注意下さい。
○県外から
航空機
東京-秋田 1時間5分大阪-秋田 1時間20分
名古屋-秋田 1時間10分
札幌-秋田 55分
秋田空港-秋田駅 リムジンバスで約40分
発着時刻はこちらから(秋田空港ターミナルビル様HPへのリンク)
新幹線【こまち号】
東京-秋田 4時間仙台-秋田 2時間20分